日本遺産認定
先日、今年度の「日本遺産」登録決定の発表がありましたが、
この度、石山寺は、
滋賀県の「琵琶湖とその水辺景観−−祈りと暮らしの水遺産」に
登録されました。
文化庁が認定する「日本遺産(Japan Heritage)」は,
文化庁のホームページによると、
地域の歴史的魅力や特色を通じて
我が国の文化・伝統などの文化財群が語るストーリーを
地域が主体となって総合的に整備・活用し,
国内だけでなく海外へも戦略的に発信し,
地域の活性化を図ることを目的とするものです。
石山寺は、琵琶湖から流れ出る唯一の川「瀬田川」の右岸に建立され、
その川の流れとともに1300年もの歴史を刻んできました。
そもそも、この場所は、
約6000 − 7000年も前から、
人々は琵琶湖や瀬田川の恵みを受けて
暮らしていた地でした。
現在駐車場となっている場所からは、
関西屈指の縄文時代早期の遺跡「石山貝塚」が発掘されています。
創建以前の飛鳥時代、
川原寺の中金堂の礎石に使用する石は、
この場所から切り出され、
瀬田川を使って運んでいたと思われます。
奈良時代に入り、石山寺の創建の際も、
必要な資材は川を使って運ばれていたことが
『正倉院文書』から判明しています。
平安時代以降、流行した石山詣での人々は、
打出浜と石山寺の間を舟で行き来しました。
瀬田唐橋と石山寺の間にあったと推測される
「山吹の崎」「いかが崎」は歌枕ともなっており、
藤原道綱母の『蜻蛉日記』にも登場します。
石山寺の草創と観音の功徳を記した「石山寺縁起絵巻」(重要文化財)は、
開基である老弁僧正が、
琵琶湖の南岸で釣りをしている老人(実は比良明神)に出会う場面から始まり、
宇多法皇の御幸、大津の浦の馬借、歴海和尚と龍王たち、殺生禁断、
紫式部の起筆、瀬田唐橋、琵琶湖の嵐で白馬に助けられる少女など、
多くの場面で、水辺とその周辺で暮らす人々の姿が
生き生きと描かれています。
なかでも、紫式部が当寺に七日間籠り、
湖面に映える月を見て『源氏物語』を書き始めたという場面が
最も知られています。
これらから、琵琶湖と瀬田川は石山寺と密接に関わり、
それぞれの文化の形成に少なからず影響を与えていたといえるでしょう。
そして、現在、
いくつかの石段を登り、
やっとたどり着く月見亭横からの瀬田川・琵琶湖の風景に
癒される方は少なくないと思います。
今回の日本遺産への登録が、
水を通じて、石山寺の歴史、文化、環境を
より深く知っていただく機会となりましたら幸いです。
 2014年4月8日撮影
2014年4月8日撮影*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
本尊如意輪観世音菩薩御開扉
↓クリックすると詳細がご覧いただけます。
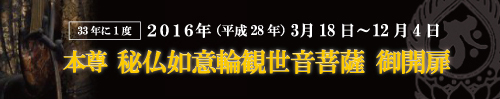
期間:2016年3月18日から12月4日まで
※本尊如意輪観世音菩薩さまの特別拝観と豊浄殿をご覧になる場合は、
石山寺入山料(600円)と御本尊さま特別拝観料(500円)と
豊浄殿入館料(300円)が一緒になった
「セット券」(1,200円、30名以上の団体は1,100円)をご利用ください。
セット券は、志納所(東大門から100メートル進んだ右側)にて、
午前9時から午後3時30分までお取扱いしております。
なお、本堂内陣における本尊如意輪観世音菩薩の特別拝観の受付は、
午前8時から午後4時まで、
豊浄殿の開館時間は午前9時から午後4時(入館は午後3時45分まで)ですので、
お時間に余裕を持ってご来寺いただけましたら幸いです。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
御開扉記念特別展示(石山寺と紫式部展)
「ほとけの誓ひおもきいしやま」
2016年3月18日から12月4日まで
詳細はこちら↓

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
「54歩で読む『源氏物語』」展
詳細はこちら↓

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
===========================
お問い合わせ
石山寺 Tel:077-537-0013
===========================
石山寺周辺の観光情報、御本尊御開扉
ボランティアガイドのお問い合わせ
石山観光協会 Tel:077-537-1105
===========================
駐車場のお問い合わせ
石山寺観光駐車場 Tel:077-534-1600
===========================



